
「固定資産税はきちんと払っており、証明する領収書もある」とのことだけど、土地にかかる固定資産税ならまだしも、未登記の建物に対しどうやって〝建物〟の固定資産税を払うんだ?固定資産税は1月1日に航空写真にて建物を確認し課税の対象としていると聞きました、建物の登記はすることが望ましいが必ずしも義務ではないとあります。ファクトチェックをお願いします
1. 「未登記の建物に対してどうやって〝建物〟の固定資産税を払うのか」
事実:
未登記の建物であっても、固定資産税は課税されます。固定資産税は、法務局の登記簿に登録されているかどうかではなく、毎年1月1日時点(賦課期日)の現況に基づいて課税される仕組みです。自治体(市区町村)は、登記簿だけでなく、現地調査や航空写真の比較、住民からの情報などを活用して、建物の存在を把握します。これにより、未登記であっても「家屋補充課税台帳」に登録され、所有者とみなされる人に納税通知書が送付されます。
- 仕組み: 自治体は「固定資産課税台帳」を作成し、そこに土地や建物の情報を記録します。未登記建物の場合は、登記簿ではなく現況調査に基づいて「家屋補充課税台帳」に記載され、課税対象となります。
- 支払い: 納税通知書には、土地と建物それぞれの課税額が明記されており、未登記建物の場合も「家屋番号」が空欄または「未登記」と記載されることがあります。それでも、建物分の固定資産税が含まれているため、所有者はその通知書に従って支払います。領収書があれば、それが証明となります。
結論:
未登記の建物であっても、自治体がその存在を確認すれば固定資産税が課され、支払いが可能です。したがって、「固定資産税をきちんと払っており、領収書もある」という主張は、未登記建物であっても問題なく成り立ちます。ただし、納税通知書に建物が正しく記載されているかどうかは、個別のケースで確認が必要です。
2. 「固定資産税は1月1日に航空写真にて建物を確認し課税の対象としているのか」
事実:
固定資産税の賦課期日は確かに毎年1月1日であり、この時点で存在する固定資産(土地・建物・償却資産)が課税対象となります。ただし、「航空写真にて建物を確認する」というのは、課税対象を把握する手段の一つに過ぎません。
- 確認方法: 自治体は複数の方法で建物の存在を確認します。
- 航空写真: 国土地理院や民間企業が撮影した航空写真を活用し、新旧の写真を比較して新築や増築を把握することがあります。ただし、これが唯一の方法ではなく、すべての自治体が毎年1月1日に航空写真を撮影するわけではありません。
- 現地調査: 自治体職員が実際に現地を訪れ、建物の有無や状態を確認します。
- 申告や情報提供: 住民や近隣からの情報、建築確認申請のデータなども参考にされます。
- 課税のタイミング: 航空写真や現地調査は随時行われており、1月1日時点で存在が確認された建物がその年度(4月からの1年間)の課税対象となります。未発見の場合は課税されないこともありますが、後で発見されれば過去5年分まで遡って追徴される可能性があります(地方税法による時効は5年)。
結論:
「1月1日に航空写真で確認」というのは部分的に正しいが、やや単純化された表現です。航空写真は重要なツールですが、課税対象の確認はそれに限らず、年間を通じて行われる調査の結果が反映されます。したがって、この点は厳密には「航空写真だけではない」と補足が必要です。
3. 「建物の登記はすることが望ましいが必ずしも義務ではないのか」
事実:
建物の登記(表題登記)については、不動産登記法で一定の義務が定められていますが、実際の運用では曖昧な部分があります。
- 法律上の義務: 不動産登記法第47条では、「新築した建物または表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない」とされています。怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があると明記されています(同法164条)。
- 実態: しかし、この過料が実際に適用された事例はほとんど報告されておらず、未登記建物が全国に多数存在する現状があります。特に、古い建物や田舎の家屋では、登記せずに放置されているケースが珍しくありません。登記は所有者が自ら申請するものであり、自治体や法務局が強制的に登記することはありません。
- 望ましい理由: 登記をしないと、所有権を第三者に主張できない、住宅ローンが組めない、売却や相続時にトラブルが起きるなどのデメリットが生じます。また、土地の固定資産税軽減措置(住宅用地の特例)が適用されない場合もあり、税負担が増えるリスクもあります。
結論:
建物の表題登記は法律上義務付けられていますが、罰則がほぼ適用されないため、「必ずしも義務ではない」という認識が実質的に広がっています。ただし、法的に正しくは「義務」であり、望ましいだけでなくトラブル回避のために強く推奨されます。
総合的なファクトチェック
森山幹事長の「固定資産税はきちんと払っており、証明する領収書もある」という主張は、未登記建物であっても自治体が現況を把握していれば課税され、支払いが可能なので、事実として矛盾はありません。ただし、以下の点を補足します:
- 未登記建物が課税対象となるには、自治体がその存在を把握している必要があります。もし把握されていなければ課税されず、逆に後で発見されると追徴の可能性があります。
- 「航空写真で1月1日に確認」というのは正確ではなく、航空写真は調査手段の一つであり、年間を通じた調査が課税に反映されます。
- 登記は法律上義務ですが、実質的には未登記でも罰則が適用されにくいため、「義務ではない」と誤解されがちです。

森山幹事長の一連のポストは、本来さほど問題にならない事に罪があるかのように批難が散見します。この情報のリーク元はどこなのでしょうか?あわせて森山幹事長の過去の言動や活動、そして最近の動向を詳しく知りたいです
ご質問ありがとうございます。森山裕自民党幹事長に関する一連のポストや報道、特に「未登記の建物に対する固定資産税」問題が注目を集めている件について、情報のリーク元を特定することは困難ですが、推測とともに可能な範囲で回答します。また、森山幹事長の過去の言動、活動、最近の動向についても詳しくお伝えします。
1. 情報のリーク元の推測
森山幹事長に関する「未登記建物の固定資産税」問題がXやメディアで取り沙汰されている背景には、具体的なリーク元の明示はありません。ただし、以下の可能性が考えられます:
- 政治的対立勢力: 自民党内部の派閥対立や野党が、森山氏の立場(幹事長という党のナンバー2)を弱体化させる目的で情報を流した可能性。自民党は2024年9月の総裁選や10月の衆院選での敗北後、党内での責任論や調整が続いており、森山氏への批判が高まるタイミングでの情報リークは政治的意図を疑わせます。
- メディア調査: 朝日新聞や読売新聞などの大手メディアが、独自の取材で森山氏の資産状況や固定資産税の支払い記録を調査し、未登記建物の問題を発見した可能性。政治家の資産公開制度や自治体の課税データを基に、記者が裏を取った結果が報道され、Xなどで拡散された形が考えられます。
- 地元関係者: 森山氏の選挙区である鹿児島4区の地元住民や関係者が、未登記建物の存在を知っていて、メディアやSNSを通じて情報を提供した可能性。地元の不動産事情に詳しい人物がきっかけとなったケースも想定されます。
- 公的機関の内部情報: 自治体(鹿児島市など)の税務担当者や法務局関係者が、意図的または偶発的に情報を外部に漏らした可能性は低いものの、完全に否定はできません。
具体的な証拠がないため、リーク元は不明ですが、2024年10月の衆院選での自民党の大敗や「政治とカネ」問題への国民の不信感が背景にあり、森山氏がターゲットとして浮上したタイミングは政治的な文脈と一致します。Xでの批判的な投稿(例: 「固定資産税を誤魔化してる」「脱税」など)は、この不信感を反映した感情的な反応とも言えます。
2. 本来さほど問題にならない事への批判
森山幹事長の「未登記建物の固定資産税を払っている」という主張が、過剰に問題視されているとのご指摘について、その通り一部で誤解や誇張が見られます。私の前回の回答でも説明した通り:
- 未登記建物でも自治体が現況を把握すれば固定資産税が課税され、支払いが可能です。
- 登記は法律上義務(不動産登記法第47条)ですが、罰則がほぼ適用されないため、未登記建物は日本全国に多く存在し、珍しいケースではありません。
しかし、森山氏への批判が過熱する理由は以下が考えられます:
- 政治家の説明責任: 幹事長という要職にある人物が、国民に厳しい税負担を求める一方で、自らの資産管理に不透明さがあると映ると、「ダブルスタンダード」と見なされやすい。
- タイミング: 2024年の衆院選での自民党敗北や「政治とカネ」問題(裏金事件など)が国民の不信感を高めており、些細な事案でも火種になりやすい状況。
- SNSの拡散力: Xなどのプラットフォームでは、感情的な投稿が拡散されやすく、事実が検証される前に批判が広がる傾向があります。
したがって、本件は法制度上は大きな問題ではない可能性が高いものの、政治的・社会的な文脈で過剰に注目されていると言えます。
3. 森山裕幹事長の過去の言動・活動
森山裕(もりやま ひろし、1945年4月8日生まれ、79歳)は、長年にわたり自民党内で要職を務めてきたベテラン政治家です。以下に経歴と過去の言動・活動をまとめます。
経歴
- 出自と初期キャリア: 鹿児島県出身。働きながら高校夜間課程を卒業し、鹿児島市議会議員を7期(議長を5期)務めた「たたき上げ」の政治家。1983年に参議院議員に初当選。
- 衆議院議員: 2004年の鹿児島5区補選で当選し、以降8期連続当選(現在は鹿児島4区)。
- 党内の役職:
- 農林水産大臣(2014年-2015年)
- 国会対策委員長(2017年-2021年、歴代最長4年)
- 総務会長(2021年-2024年)
- 幹事長(2024年9月30日~現在)
- 派閥: 旧森山派(石原派を引き継ぐ)を率いるが、派閥解消後は無派閥。
過去の言動・活動
- 農林族の代表: 農林水産分野での活動が顕著。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に慎重姿勢を示し、2010年に「TPP参加の即時撤回を求める会」を結成し会長に就任。日本の農業保護を重視。
- 郵政造反: 2005年の郵政民営化法案に反対し、自民党公認を失い無所属で出馬。再選後、2006年に復党(郵政造反組復党問題)。
- 調整力: 国会対策委員長時代、野党との交渉で硬軟織り交ぜた手腕を発揮。「野党にも太いパイプを持つ」と評され、党内随一の調整力で知られる。政治の師は二階堂進元幹事長。
- 政治とカネへの対応: 2024年の自民党派閥裏金問題では、関係議員の事情聴取を主導。しかし、自身も過去の選挙で政党交付金1500万円を全額選挙運動費に計上していたことが批判され、「党勢拡大のため」と弁明。
特徴的な言動
- 「選挙で国民の信任を受ければ差別は続かない」(2024年10月14日): 裏金問題で非公認となった議員の役職起用を容認する姿勢を示し、物議を醸す。
- 「大変厳しい国民の批判があった」(2024年10月27日): 衆院選敗北後、NHK番組で反省を表明。
4. 最近の動向(2024年9月~2025年3月)
森山幹事長の最近の動向は、石破茂総裁の下での党運営と衆院選後の対応に焦点が当てられます。
幹事長就任と衆院選
- 2024年9月30日: 石破総裁が幹事長に起用。石破氏の早期解散方針に強く進言し、10月9日に衆院解散、10月27日に投開票という短期決戦を主導。
- 2024年10月27日衆院選: 自民党は過半数を割り込む大敗。与党(自民・公明)は233議席(過半数233)に届かず、森山氏への責任論が浮上。しかし、「責任を果たしたい」と続投意欲を示す。
選挙後の対応
- 裏金問題: 非公認候補の党支部に2000万円を支給した問題で、「ルールに基づいている」と弁明するも、「説明不足」と反省を述べる(10月27日)。
- 予算案調整: 2025年度予算案を巡り、少数与党として維新や国民民主党との協議を主導。「筋を通した決着を」(3月15日、福島市講演)と発言。
- 党員減少: 2024年の党員数が6万人減の102万人に。裏金問題と衆院選敗北が影響とされ、「課題はあるが100万人台を維持」とコメント(3月5日)。
未登記建物問題
- 2025年3月頃: Xで「固定資産税を誤魔化してる」「脱税」との批判が拡散。森山氏は「きちんと払っており領収書もある」と反論。報道の詳細は不明だが、党内や世論の不信感が再燃。
評価と批判
- 評価: 「森羅万象を扱う影の総理」(朝日新聞、3月9日)と称されるほど、党運営での存在感が大きい。
- 批判: 衆院選敗北の責任や、未登記建物問題での説明不足が槍玉に。「公民権停止を」との過激な声もXで散見。

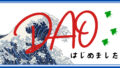

コメント